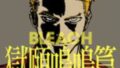「銅羅衛門はどこで読める?」
「あらすじや登場人物について詳しく知りたい!」
「見どころや評判は?」
と気になっている方も多いでしょう。
この記事では、そんな方のために、「銅羅衛門」を徹底解説!
どこで読めるのか、物語のあらすじ、登場人物の魅力やファンが注目する見どころポイント、レビュー、さらには、作品を生み出した日野日出志氏についてもご紹介し、作品の魅力を深掘りしていきます。
- 銅羅衛門はメルカリで読める
- あらすじや主要な登場人物に関する詳細
- 作品の見どころや他の読者の感想レビュー
銅羅衛門はどこで読める?メルカリで読めます。

まずは「メルカリ」をチェックするのが最も現実的
『銅羅衛門』を読みたいと考えている方にとって、もっとも現実的な入手手段はフリマアプリ「メルカリ」での購入です。
『銅羅衛門』が収録されている雑誌『パロディ・マンガ大全集』(奇想天外社/1981年12月発行)は、すでに絶版のため、通常の書店では手に入りませんが、メルカリでは個人間取引で出品されていることがあります。
メルカリで購入する大きなメリットは以下のとおりです。
- 在庫の回転が早く、出品が頻繁にあるため、タイミングさえ合えば比較的早く入手できる
- 価格交渉や送料込みの出品が多く、他の中古市場よりお得に買える可能性がある
- 実物の写真付き出品なので、状態の確認がしやすく、安心して購入しやすい
希少な書籍ほど、タイミングとスピードがものを言います。定期的にアプリをチェックし、通知機能などを活用することで、より早く希望の一冊にたどり着けるでしょう。
中古市場での他の選択肢
前述のメルカリに加え、以下のようなルートでも入手可能性があります。
- ヤフオクやモバオクなどのネットオークション:希少本が出品されることもあり、入札形式で価格が上下する
- 駿河屋、日本の古本屋などのオンライン古書店:古書業者が在庫管理しているため、状態が詳細に明記されている
- リアル店舗の古書店やまんだらけなどの専門店:店頭で状態を直接確認できる点が魅力
これらのルートは、出品頻度が低めである反面、稀に帯付きや保存状態の良好なものが見つかることもあり、コレクターにとっては宝探しのような楽しみもあります。
なぜ今でも読める手段が限られているのか?
『銅羅衛門』は一度も単行本化されておらず、また電子書籍にもなっていません。
さらに、発表当時の『パロディ・マンガ大全集』自体が臨時増刊号という特殊な位置付けだったため、初版の発行部数も限られていたと考えられます。
再録や復刊の情報も出ておらず、出版側からの再評価がなされていない点も、入手難易度が高い理由の一つです。
入手時の注意点
希少性ゆえに、価格が高騰していることも多く、状態に見合った価格であるかを見極める目も必要です。
特に以下のポイントには注意してください。
- 出品写真が鮮明で、全体の状態(表紙、背表紙、ページの焼けなど)が確認できるか
- 書き込みや破れの有無、付属品(帯、付録)の有無
- 過去の相場と比較して、極端に高額でないかどうか
中でもメルカリなどのフリマアプリでは、写真と説明文だけが頼りになるため、わからない点はコメント欄で質問しておくと安心です。
▼メルカリ公式サイト
銅羅衛門はこちらから
作品のあらすじ・ネタバレ・概要
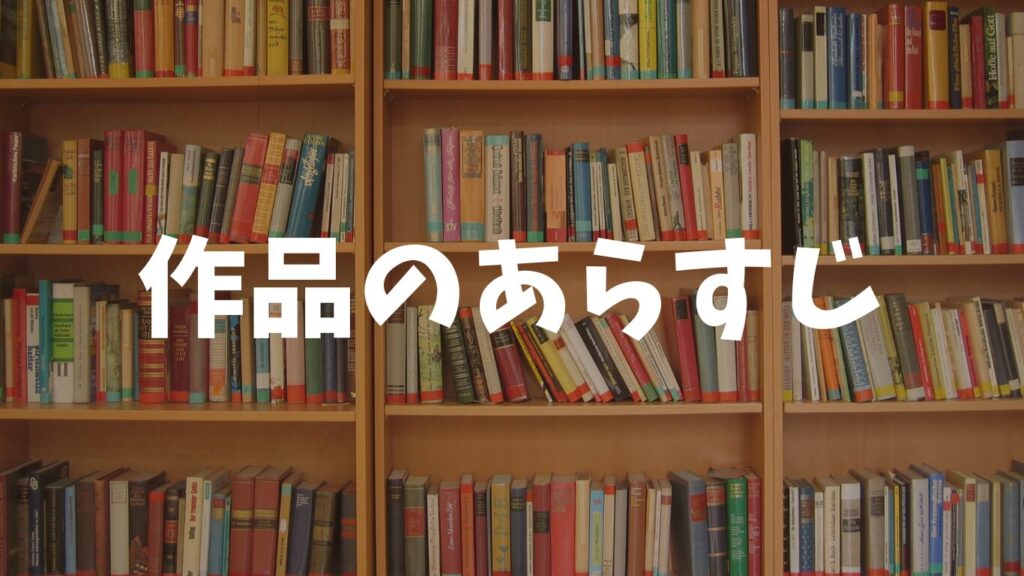
概要
日野日出志×藤子・F・不二雄――異色すぎる化学反応
『銅羅衛門』は1981年に発表された日野日出志先生による短編パロディ漫画です。
本作は、藤子・F・不二雄先生の国民的人気作『ドラえもん』を大胆に下敷きにしながら、日野先生ならではの陰鬱でグロテスクな描写、そして社会的風刺をふんだんに盛り込んだブラックコメディとなっています。
登場人物の名前も「のぶた」「銅羅衛門」「シャイアン」「ソネ夫」など、原作のキャラクターをもじったネーミングが多く、親しみやすさと不気味さが絶妙に混在しています。
その結果、原作の持つ明るく温かな雰囲気は一切排除され、読む者を戦慄させる“裏ドラえもん”的世界が展開されます。
単行本未収録の幻の一編
『銅羅衛門』は奇想天外社が1981年12月に刊行した雑誌『パロディ・マンガ大全集』のみに掲載された作品です。
単行本や文庫本などへの収録は一切なく、復刊もされていないため、今日では“知る人ぞ知るカルト作”として語り継がれています。
日野作品の中でも特にレア度が高く、その特異性からコアな漫画ファンの間で長年話題となってきました。
あらすじ
日常のいじめから始まる、常軌を逸した復讐劇
物語の主人公は、クラスメイトから理不尽な仕打ちを受け続ける少年「のぶた」。
彼は「シャイアン」や「ソネ夫」から暴力やからかいの標的にされ、毎日を苦痛の中で生きています。
そんなある日、未来からやってきた「銅羅衛門」が、彼の前に現れます。
銅羅衛門が持ち出したのは、「ミニ地獄マシン」と呼ばれる恐るべき道具。
この機械は、写真を使って対象者を縮小・捕獲し、マシン内に再現された“地獄”であらゆる拷問にかけられるというもの。
のぶたは迷うことなく、憎しみを込めてシャイアンとソネ夫の写真を挿入し、凄絶な復讐を開始します。
地獄の描写がエスカレート
マシン内で展開されるのは、もはや子供向けとは到底呼べない凄惨な光景の数々。
血の池、針山、ノコギリでの切断、石うすでの圧殺など、読者の想像力に強烈なインパクトを与える描写が続きます。
原作の『ドラえもん』にあった、優しさやユーモアとは真逆の、破壊的な世界観が全開で描かれています。
ネタバレ
復讐の果てに待つ“本当の地獄”
恐怖のミニ地獄マシンでの復讐に快感を覚えはじめるのぶたと銅羅衛門。
しかし、物語はここで意外な方向に進みます。
この機械は、銅羅衛門が“のぶたの貯金箱の中身”を元手に、地獄界の通販でローン購入した商品だったのです。
ある日、のぶたがその貴重な小遣いをうっかりトイレに流してしまったことで、ローンの支払いが不可能に。
その結果、地獄から鬼の取り立て人が現れ、借金を踏み倒した報いとして、二人を強制的に地獄送りにしてしまいます。
因果応報のブラックな結末
最終盤では、のぶたと銅羅衛門が、かつて彼らが他人に対して行ったのと同じように、血の池や火あぶり、釜茹でといった責め苦を受け、「あついよ〜」「たすけて〜」と叫びながら地獄でのたうちまわる姿が描かれます。
ここに描かれているのは、“復讐と傲慢の末路”という重いテーマであり、読む者に不気味な余韻と皮肉なメッセージを残して幕を閉じます。
主な登場人物
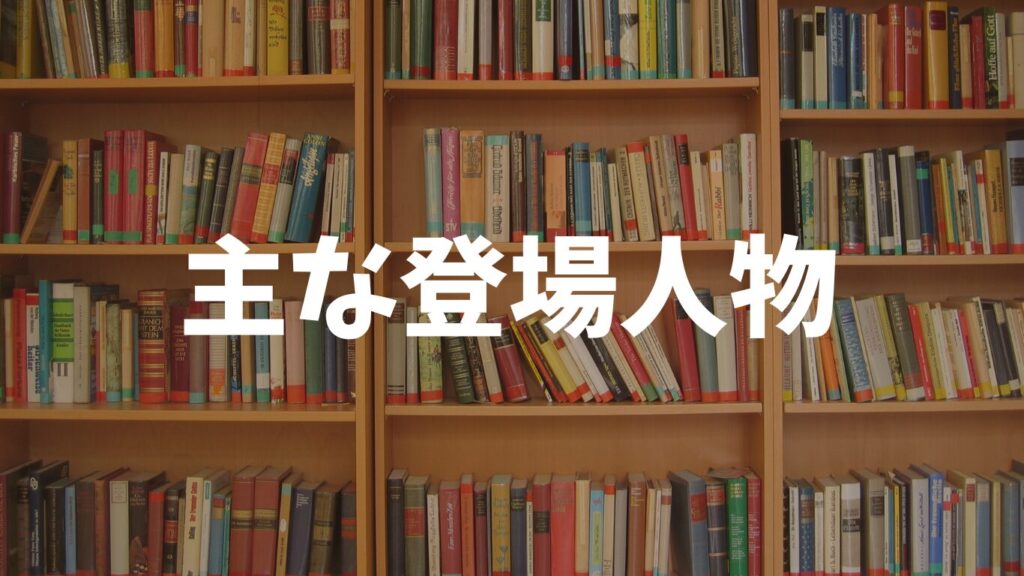
『銅羅衛門』には、原作『ドラえもん』の主要キャラクターたちを風刺的に変形させた登場人物が配置されており、ブラックユーモアとグロテスクな世界観を際立たせています。
それぞれのキャラクターは、原作の役割をベースにしながらも、まったく異なる方向へと歪められて描かれています。
銅羅衛門
物語の中核を担う謎の存在で、外見こそドラえもんを思わせますが、その性質は対極にあります。
のぶたの復讐心を煽り、迷いなく「ミニ地獄マシン」を提供する姿は、読者に強烈な違和感を与えます。
表情や言動は冷淡で、どこか他人事のように惨劇を見つめる姿には、機械的というよりも不気味さすら漂います。
道具の用途も救済ではなく加虐であり、「助けるために来た未来の使者」という立ち位置は、皮肉なまでに歪められています。
のぶた
原作ののび太にあたるキャラクターですが、受け身で泣き虫な一面だけでなく、報復という名の暴力に陶酔していく内面の変化が描かれます。
物語序盤では被害者の立場に立つものの、「ミニ地獄マシン」の存在が彼の中に潜んでいた攻撃性を解放していきます。
やがて彼は、自らの意志で復讐を実行し、加害者の立場へと変貌していきます。
その過程はまさに「いじめられっ子の闇」を可視化したものであり、単なる被害者・加害者の枠に収まらない複雑な心理描写が特徴です。
シャイアン
原作のジャイアンのような立ち位置で、圧倒的な暴力と威圧でのぶたを支配していた少年。
彼の描写は極端にデフォルメされ、もはや悪意の象徴として登場します。
「ミニ地獄マシン」によって、これまで他人に浴びせていた暴力を自ら味わうことになる展開は皮肉に満ちており、作品全体のテーマである“因果応報”を体現する存在でもあります。
無残な末路がもたらす読後感の重さは、単なる復讐劇以上のものを感じさせます。
ソネ夫
シャイアンの影に隠れつつも、同様に陰湿な言動を繰り返す少年で、原作のスネ夫をモデルとしています。
本作ではその陰険さがさらに強調され、ずる賢く小賢しいキャラクターとして登場しますが、最終的には自分が弄んでいた存在からの報復を受けることになります。
石うすで押し潰されるという描写は極めて残虐で、「調子に乗った者の末路」として印象的なシーンとなっています。
歪んだ“ドラえもんワールド”の住人たち
これらのキャラクターたちは、誰もが知る『ドラえもん』の登場人物を基にしながら、日野日出志の持つ独特な美学と恐怖のフィルターを通すことで、まったく別物に変貌しています。
原作ではコミカルに描かれていた関係性や性格が、本作では過激にデフォルメされ、それぞれの“闇”が強調される形で再構築されているのが特徴です。
作品の見どころ
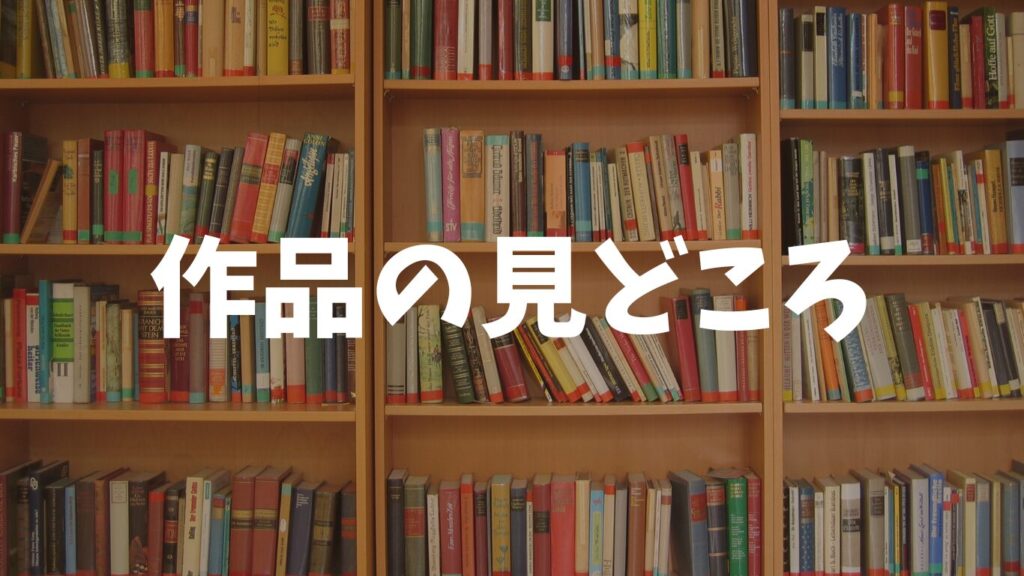
『銅羅衛門』は、ただのパロディやホラーではありません。
読者の心に突き刺さる独特の「不快さ」と「おかしみ」を共存させた、稀有な作品です。
以下では、その魅力を構成するいくつかの重要な要素を紹介します。
常識を覆す“原作破壊”の衝撃
本作最大の特徴は、誰もが親しんだ『ドラえもん』という温かく穏やかな世界を、あえて冷酷でグロテスクな世界へとねじ曲げている点です。
日野日出志先生の手にかかると、ユーモアと夢の象徴だった未来ガジェットが、恐怖と絶望の装置へと変貌。
もはやパロディの枠を越えた、「創造的破壊」とも呼べる再構築がなされています。
登場人物たちの性格・言動も大胆に書き換えられており、善悪の境界が曖昧なまま物語が進行していく構成は、読者に心理的な揺さぶりを与えます。
原作への知識があるほど、そのギャップは衝撃的に響きます。
グロテスク描写が生み出す生理的恐怖
前述の通り、本作では「ミニ地獄マシン」によって繰り広げられる拷問シーンが、視覚的にも精神的にも強烈なインパクトを放っています。
切断、刺突、圧死、流血などの描写が容赦なく展開される一方で、過度なリアリズムには頼らず、あくまで日野作品らしい“異形の幻想”として表現されているのもポイントです。
一見コミカルなキャラクターデザインとの落差が、かえって残虐性を強調しており、「怖いのに目を背けられない」不思議な吸引力を生んでいます。
ブラックユーモアの毒と知性
本作の魅力は、グロだけではありません。
物語の随所に仕込まれた皮肉や風刺が、ただ怖いだけで終わらせない奥深さを与えています。
たとえば、「地獄のローン契約」や「支払い不能による永遠の罰」といった設定は、現代社会の債務・搾取構造を思わせるブラックジョークであり、単なる悪趣味ではない風刺性が潜んでいます。
また、銅羅衛門の妙に丁寧な口調や、のぶたの高揚した独白など、どこか滑稽で笑える要素も織り交ぜられており、読者は「怖いのに笑ってしまう」二重のリアクションを引き出されます。
時代背景とパロディ精神の価値
1980年代初頭という時代に、ここまでタブーを踏み越えた内容が商業媒体に掲載されたという事実は、それ自体が文化的な事件とも言えます。
国民的キャラクターを大胆に借用し、暴力と死を通じて人間の本性をあぶり出すという手法は、今の出版状況では到底実現不可能な“表現の自由”の産物です。
当時の読者に与えた衝撃と、それが現在でも語り継がれる理由のひとつは、この「許されざるパロディ」が、表現の限界に挑戦していたからにほかなりません。
すべてが“読後のざらつき”に繋がる
こうした要素が複雑に重なり合い、『銅羅衛門』は単なる読み物ではなく、「読後に残る感触」として読者の記憶にこびりつく作品となっています。
笑ったはずなのに心が冷える、可愛い絵なのに悪夢を見る──そうした相反する感情を同時に喚起することができる、唯一無二の読書体験こそが、本作の真の見どころと言えるでしょう。
感想・レビュー・口コミ・評価
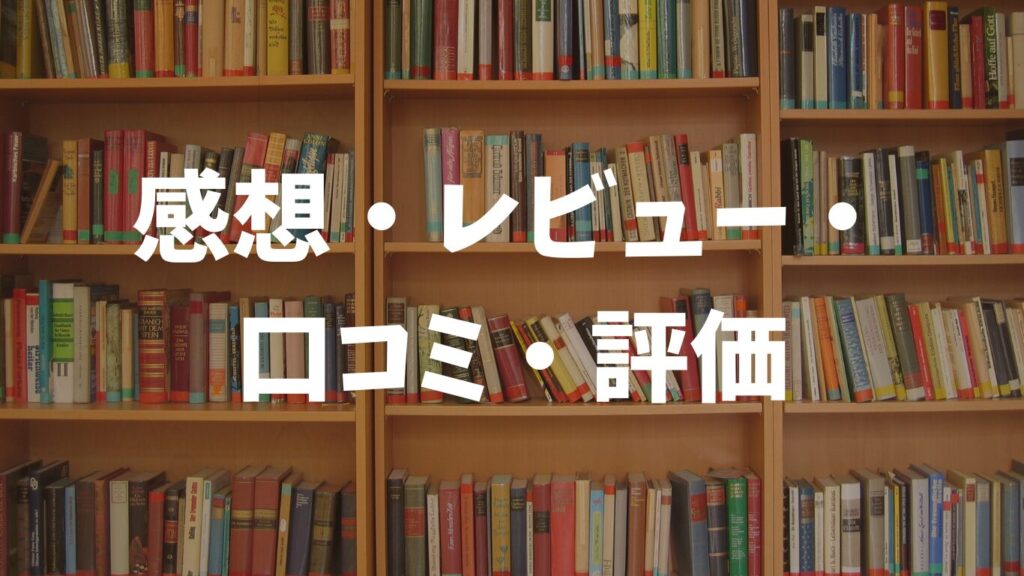
『銅羅衛門』に寄せられる感想や評価は、決して一様ではありません。
賛否が分かれるのは、それだけ本作が“普通”ではないという証でもあります。
読んだ人の心に深く残る、強烈な読書体験として語られることの多い本作について、主な反応をいくつかの視点から紹介します。
忘れられないインパクトに圧倒される読者続出
多くの読者レビューでまず語られているのは、「一度見たら頭から離れない」という強烈な印象です。
可愛らしいキャラクター造形をベースにしながらも、凄惨な描写と異様な空気感が立ち上がる構成は、「トラウマ級」「夢に出そう」といった感想を呼び起こしています。
国民的アニメのイメージを逆手に取った表現は衝撃的で、特に原作『ドラえもん』に親しんでいた読者ほどそのギャップに戸惑い、同時に強く惹きつけられる傾向があります。
作品性の高さを評価する声も多い
『銅羅衛門』は単なる「悪趣味なパロディ」ではなく、完成度の高いホラー短編として評価されている点も特筆すべきポイントです。
ブラックユーモアの効いたセリフ回し、無慈悲な運命に巻き込まれていく登場人物たち、そして読後に広がる不気味な余韻。
これらの要素が複雑に絡み合うことで、「ただグロいだけではない」「むしろ風刺的で社会批評性すら感じる」といった意見も見受けられます。
また、物語の終盤に描かれる皮肉なオチに対しては、「突き放すようでいて鋭い」「救いがないのに妙に納得させられる」との反応もあり、読者の受け取り方に深みを与えています。
賛否両論の“問題作”
その一方で、「読む人を選ぶ」との声が絶えないのも事実です。
特にホラーやゴア描写に慣れていない人からは、「気分が悪くなった」「ここまで過激である必要があるのか」という批判的な感想も上がっています。
「日野日出志作品に耐性があるかどうか」で、本作の印象は大きく変わるといっても過言ではありません。
中には、「作品そのものというより、自分の中にある恐怖や不快感を刺激されることが辛かった」という、感情面の揺さぶりに戸惑った読者の声もあり、エンタメとして楽しめるかどうかは個々人の感受性に大きく依存します。
レア度とカルト的人気による“伝説化”
『銅羅衛門』はその内容の特殊性に加え、現在では入手困難な希少性も手伝って、「知る人ぞ知る幻の怪作」として語られがちです。
実際、「読みたくても読めない」「名前だけ聞いたことがあるが内容は知らない」といった声がSNSや掲示板で見受けられることもあり、その“幻性”が読者の好奇心をさらに煽っています。
このように、過激な内容・独自の世界観・レア度という三拍子が揃った本作は、「伝説的な怪作」「タブーを笑い飛ばした挑戦作」として、今なおカルト的な人気を誇り続けています。
読者が口を揃える“覚悟して読むべき一冊”
全体的な評価としては、「強烈だが忘れられない」「読む価値はあるが気軽には勧められない」といったスタンスが多く見られます。
読む前の心構えが問われる一冊であり、感受性が豊かな人やグロ耐性のない人には相応の注意が必要です。
それでもあえて手に取った読者の多くが、「読後に何とも言えない感情が残る」と語るように、本作には他では味わえない“読書体験”が詰まっています。
作者は日野日出志氏
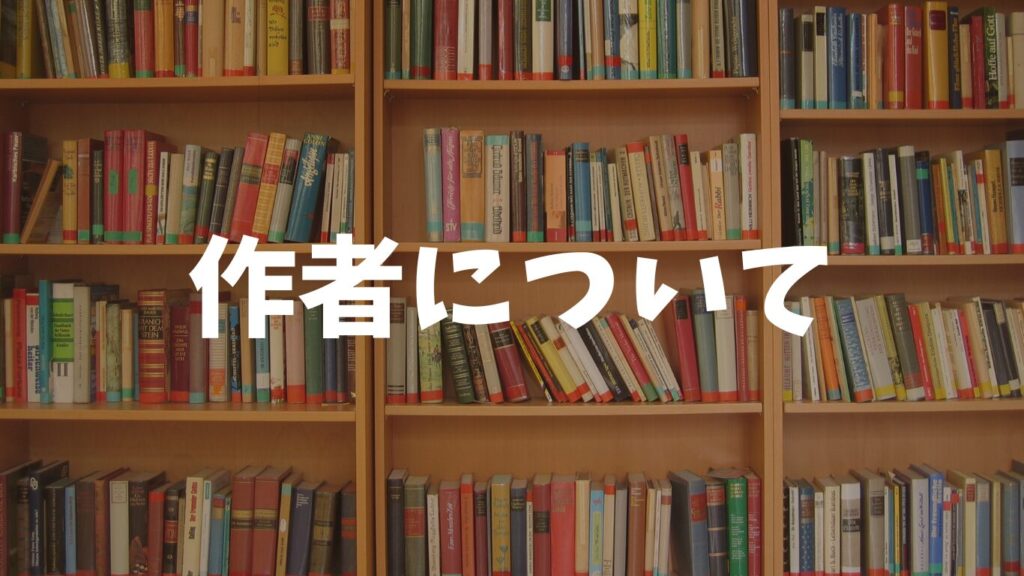
『銅羅衛門』の作者は、日本ホラー漫画界の異才として長年にわたり活躍してきた日野日出志先生です。
1946年に旧満州・チチハル市で生まれ、戦後に日本へ引き揚げた経験を持ち、少年時代の記憶や社会への違和感が作品世界の根底に色濃く反映されています。
独自の美学と世界観で築かれた“日野ワールド”
日野日出志先生の作品は、ただのホラーではありません。
不条理と狂気、幻想と悲哀が交錯する作風は、まるで悪夢のような読後感を残します。
代表作の『蔵六の奇病』や『地獄変』では、人間の内面や社会の異常性がグロテスクかつ寓話的に描かれ、多くの読者の心に爪痕を残してきました。
画風は一見荒々しく、時に幼稚とも取れるタッチながら、そこに込められたテーマは深く哲学的です。
人間の業、孤独、死への恐怖といった要素が、独特の“日野ワールド”として確立されています。
国内外から評価されるカルト的人気
日野先生の作品は、日本国内の熱狂的なファン層に支持されているだけでなく、海外でもカルト的な人気を誇ります。
アメリカやフランス、スペインなどで翻訳され、「日本のホラー漫画文化を象徴する存在」として紹介されることもあります。
また、その絵柄とテーマ性が海外のアートシーンやオルタナティブコミックの文脈でも注目され、展覧会などに取り上げられることもあります。
『銅羅衛門』はキャリアの中でも異色の存在
『銅羅衛門』は、そんな日野日出志作品の中でもとりわけ異色の一作です。
前述の通り、本作は国民的キャラクターをベースにしたパロディ作品であり、彼の通常の創作スタイルとは一線を画しています。
ただし、日野先生の得意とする恐怖表現、風刺、そして登場人物の心理描写の鋭さは、本作にもしっかりと息づいており、あくまで“日野作品”としての核は保たれています。
興味深いのは、作者自身が『銅羅衛門』を「代表作とは思っていない」と語ったとされる点です。
パロディであること、単行本化されていないこと、そして作品の過激性が、日野先生にとって少しばかり“異質”だったのかもしれません。
怪奇の巨匠が見せる、意外な素顔
意外なことに、日野先生本人はホラーというジャンルそのものを「本当はあまり得意ではない」と語っていたことがあります。
「怖がらせるために描いているわけではない」「むしろ人間の弱さや孤独を描きたい」といった発言からは、彼が作品に込めるテーマが恐怖だけでなく、より普遍的な人間の苦しみや哀しみに根ざしていることがうかがえます。
また、駆け出し時代には経済的に困窮し、水木しげる先生から励ましを受けたエピソードも知られています。
こうした人間味のある背景が、作品のどこか哀愁を帯びた空気にも影響を与えているのかもしれません。
現在もなお第一線で活躍中
年齢を重ねた今も、日野日出志先生は創作への情熱を失っていません。
銚子電鉄のマスコットキャラクター「まずえもん」のデザインを手がけるなど、ジャンルにとらわれず活動の幅を広げています。
ホラー漫画の枠を超えた芸術的表現者として、今後もどのような作品を見せてくれるのか、多くのファンが注目を続けています。
銅羅衛門はどこで読める?まとめ
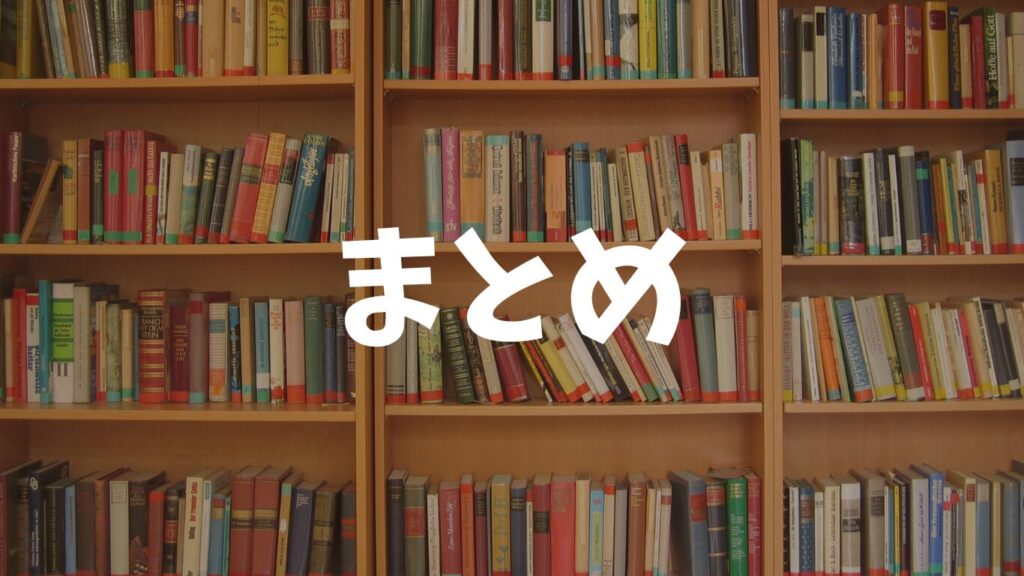
- 『銅羅衛門』は日野日出志による『ドラえもん』の短編パロディ漫画である
- 現時点で公式の電子書籍化・単行本化はされていない希少作
- 主な入手方法はメルカリなどのフリマアプリでの中古購入
- 「ドラえもん」のパロディでありながらホラー要素が強い
- 主人公の少年はいじめられっ子で、復讐が主題となる
- 銅羅衛門は暗い性格で、復讐の手段を次々と提供する
- 地獄・呪い・死後の世界といった重いテーマが描かれる
- 絵柄はギャグ寄りだが、内容はグロテスクで陰鬱
- 銅羅衛門は「四次元ツール」ではなく「地獄具現道具」を出す
- ラストでは復讐が裏目に出て、主人公が地獄に堕ちる展開
- 因果応報・カルマといった仏教的モチーフが使われている
- 原作への風刺や社会風刺も込められたブラックユーモア作品
- シリアス展開とギャグ要素のギャップが強烈な印象を残す
- 作者は日本ホラー漫画界の巨匠、日野日出志である
- ファンの間では「封印作品」「幻のパロディ」として有名